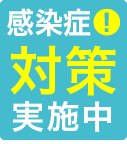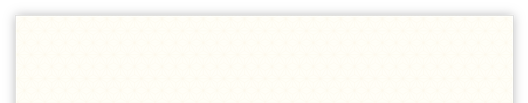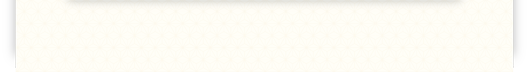日本の夏の風物詩と言えば、多くの人が思い浮かべるのが「土用丑の日」とうなぎ。 毎年7月になるとスーパーや飲食店にはうなぎの蒲焼がずらりと並び、テレビやSNSでも話題になります。 ですが、なぜそもそも夏の土用丑の日に「うなぎ」を食べる習慣ができ、今もこれほどまでに人々に愛され続けているのでしょうか。
「土用」とは何か?日本人の暦感覚
まず「土用」とは四季の節目、「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の直前約18日間を指し、特に夏の土用(7月中旬~8月初旬)は江戸時代から現代まで大事な季節の変わり目として意識されてきました。 「土用」は中国の五行思想「木・火・土・金・水」に由来し、中でも「土」の気が高まる時期とされています。 現在でも夏の土用は、体調管理や風習の節目として全国各地で重視されています。
「丑の日」とは?十二支と暦のリズム
「丑の日」は、十二支を使って日にちを数えた際の「丑」に当たる日です。 十二支は年だけでなく日付にも適応され、土用期間中に巡る「丑」の日が”土用丑の日”となります。 土用の期間は18日前後、十二支のサイクルは12日なので、年によっては一度だけでなく「一の丑」「二の丑」と2回巡る年もあります。 (2025年は7月19日と7月31日)
なぜ「うなぎ」? その起源と由来
土用丑の日にはなぜ「うなぎ」なのでしょうか。 一番有名な説は、18世紀の博学者・平賀源内が発明したというもの。 夏はうなぎの売り上げが落ちる為、うなぎ屋が源内に相談したところ「本日 土用丑の日」と大きく掲げた張り紙を勧めました。 これが大当たりし、夏にうなぎを食べる習慣が全国へと広まったのです。 この発想は当時としては斬新かつ現代のマーケティングにも通じる知恵でした。 また、「うなぎには滋養強壮効果があり、夏バテ防止に良いと古くから考えられてきました。 土用の頃は昔から食あたりや体調不良の起こりやすい時期とされ、うなぎを食べて体力をつける、という民間の知恵も背景にあります。 ちなみに「う」の付く食べ物(梅干しやうどんなど)を食べると夏負けしない、という風習も並行して各地にみられました。
夏以外にもある「土用」と「丑の日」
実は「土用丑の日」は春・夏・冬にも存在します。 ただし「うなぎ」を食べる習慣が定着しているのは、主に夏の土用丑の日です。 厳しい暑さに適応する知恵と、商売上の工夫が重なり、今では一大グルメイベントとしても根付きました。
現代の「土用丑の日」の楽しみ方とSDGs
現代では、土用丑の日はうなぎ屋の繁忙期。 家庭でうなぎを楽しんだり、高級店でこだわりの蒲焼を味わったりと楽しみ方も多様化しています。 一方で、近年は天然うなぎの資源減少など持続可能性も課題となっています。 そのため、養殖や別の魚種(ナマズやアナゴなど)を活用するなど、サステナブルな土用丑の日の過ごし方も浸透しつつあります。
まとめ
土用丑の日は、日本独自の暦感覚と知恵、そして現代的アレンジが融合した伝統文化です。 背景を知ったうえでうなぎを味わえば、その一切れがよりおいしく感じられるはずです。 今年はぜひ、ご家族や友人と話題を楽しみながら、旬のうなぎや季節の食べ物で元気な夏をお過ごしください。
直葬 家族葬 一般葬 一日葬
各宗派、各葬儀形式に対応させていただきます。
~どこまでも、家族に寄り添うお葬式~
イソラメモリアル株式会社
福岡市博多区下呉服町8-1
0120-04-3096
福岡市 中央区 博多区 東区 南区 西区 早良区 城南区 糟屋郡